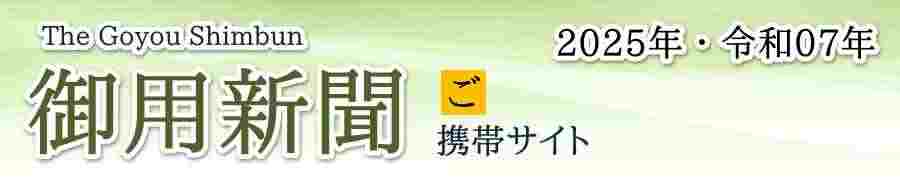各統計表の補足説明
有権者数と選挙関連
◎ 日本の有権者数・人数の推移 |
補足01:本統計表は、1965年・昭和40年~1999年・平成11年にかけては総人口を基にし、2000年・平成12年以降については日本人人口を基に作成している。補足02:2016年・平成28年6月19日、公職選挙法が改正されて選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた。2016年以降の20代の有権者数・人数と有権者数・割合には、18歳と19歳の有権者が含まれている。単位A:「日本の有権者数・人数の推移」の万人以下、千人単位については四捨五入して繰り上げてある。単位B:「日本の有権者数・割合の推移」のコンマ1以下、コンマ2の単位については四捨五入して繰り上げてある。 |
国家財政 (統計表)
◎ 日本の社会保障費の推移 (金額) |
補足01:65歳以上の医療介護年金給付は、65歳以上の医療費・介護費・年金給付費(年金給付には遺族年金などが含まれている)として使われた金額を表記している。補足02:生活保護費は、生活保護費として使われた金額を表記している。補足03:失業対策費は、1980年~2008年までは失業対策費という名目の予算の金額を表記し、2009年以降においては雇用労災対策費という名目の予算の金額を表記している。いずれも予算(予算の金額以上のお金を使うことはできない。また予算だからといって全額使い切るわけではない)として組まれた補正予算後の金額である。補足04:防衛費は、1980年~1996年までは予算(予算の金額以上のお金を使うことはできない。また予算だからといって全額使い切るわけではない)として組まれた補正予算後の金額を表記している。1997年以降については防衛費として使われた金額を表記している。単位A:65歳以上の医療介護年金給付・生活保護費・失業対策費・防衛費・社会保障費の億円以下、千万単位については四捨五入して繰り上げてある。 |
国家財政 (統計表)
◎ 地方公務員の給与の推移 (年額) |
補足01:一般行政職・警察官・消防隊員・(公立)高等学校教師・(公立)小中学校教師の給与の金額には非正規職員の給与は含まれていない。いずれの金額も正規職員に対して支払われている給与金額である。補足02:地方公務員全体の平均給与の金額の算出には、正規職員の給与に非正規職員の給与を加えた金額を用いている。単位A:一般行政職・警察官・消防隊員・(公立)高等学校教師・(公立)小中学校教師・平均給与の万円以下、千円単位については四捨五入して繰り上げてある。 |
国民経済 (統計表)
③ 平均給与と租税負担額率の推移 (年額) |
補足01:企業(会社)の労働者1人当りに出した給与の総額は、「参考資料・参考文献」のページに表記している資料を基に御用新聞が独自に算出した金額を用いている。補足02:労働者(給与所得者)1人当りの平均給与は、1年以上勤続者(役員を含む)と1年未満勤続者(役員を含む)の給与総額を合わせて、両者の総数を足して割った1人当たりの平均金額である。補足03:労働者(給与所得者)1人当りの手取り給与は、統計表「平均給与と手取り給与」内の手取り給与(年額:円)を使用している。補足04:労働者(給与所得者)1人当りの可処分所得は、統計表「平均給与と可処分所得」内の可処分所得(年額:円)を使用している。補足05:労働者(給与所得者)1人当りの租税負担額は、統計表「平均給与と手取り給与」内の(折半分)会社負担 社会保険料(税)(年額:円)と(税金)所得税+住民税(年額:円)と(折半分)自己負担 社会保険料(税)(年額:円)と統計表「平均給与と可処分所得」内の消費税額(年額:円)を足した金額から、統計表「平均給与と可処分所得」内の銀行金利(年額:円)を差し引いた金額を使用している。補足06:労働者(給与所得者)1人当りの租税負担率は、「参考資料・参考文献」のページに表記している資料を基に御用新聞が独自に算出した数値を用いている。単位A:労働者1人当りに出した給与の総額・平均給与・手取り給与・可処分所得・租税負担額の万円以下、千円単位については四捨五入して繰り上げてある。単位B:租税負担率のコンマ1以下、コンマ2の単位については四捨五入して繰り上げてある。注意点01:労働者に給与を支払う企業が負担している社会保険料(税)は、社会保険料(税)自体の支払いが無いのであれば、本来なら労働者が当然のように得ることができる給与だと考えている。その為、本統計表の租税負担額の金額と租税負担率の数値は、統計表「平均給与と手取り給与」内の(折半分)会社負担 社会保険料(税)の金額が加えて計算されている。注意点02:表示画面の制約上、当サイトでは雇用保険料の金額は掲載しておらず、租税負担額の金額と租税負担率の数値を導きだす計算式に雇用保険料の金額は含まれていない。 |
国民経済 (統計表)
② 平均給与と可処分所得の推移 (年額) |
補足01:企業(会社)の労働者1人当りに出した給与の総額は、「参考資料・参考文献」のページに表記している資料を基に御用新聞が独自に算出した金額を用いている。補足02:労働者(給与所得者)1人当りの平均給与は、1年以上勤続者(役員を含む)と1年未満勤続者(役員を含む)の給与総額を合わせて、両者の総数を足して割った1人当たりの平均金額である。補足03:労働者(給与所得者)1人当りの手取り給与は、統計表「平均給与と手取り給与」内の手取り給与(年額:円)を使用している。補足04:労働者(給与所得者)1人当りの銀行金利は、平均給与から所得税と住民税と自己負担分の社会保険料(税)を差し引いたその年の手取り給与を一年間銀行に預けて得られる金利の額を銀行金利としている。銀行金利の金額を算出した金利については、資料:「医療費負担率・年金支給開始年齢・郵便貯金の金利・消費税率の変遷表」内の郵便貯金(年利(%))を用いている。補足05:労働者(給与所得者)1人当りの消費税額は、平均給与から所得税と住民税と自己負担分の社会保険料(税)を差し引いたその年の手取り給与に、その年に得られた銀行金利を加えた金額を全額使用した場合、確実に支払う事となる税金の額を消費税額としている。消費税額を算出した税率については、統計表:「医療費負担率・年金支給軽視年齢・郵便貯金の金利・消費税率の変遷表」内の消費税(税率(%))を用いている。単位A:労働者1人当りに出した給与の総額・平均給与・手取り給与・可処分所得の万円以下、千円単位については四捨五入して繰り上げてある。単位B:銀行金利・消費税額の千円以下、百円単位については四捨五入して繰り上げてある。単位C:銀行金利の百円以下、十円単位については四捨五入して繰り上げてある。単位D:銀行金利が十円単位になってからはそのままの金額を表記している。注意点:表示画面の制約上、当サイトでは雇用保険料の金額は掲載しておらず、可処分所得の金額を導きだす計算式に雇用保険料は含まれていない。 |
国民経済 (統計表)
① 平均給与と手取り給与の推移(年額) |
補足01:企業(会社)の労働者1人当りに出した給与の総額は、「参考資料・参考文献」のページに表記している資料を基に御用新聞が独自に算出した金額を用いている。補足02:企業(会社)の(折半分)会社負担 社会保険料(税)は、「参考資料・参考文献」のページに表記している資料を基に御用新聞が独自に算出した金額を用いている。補足03:労働者(給与所得者)1人当りの平均給与は、1年以上勤続者(役員を含む)と1年未満勤続者(役員を含む)の給与総額を合わせて、両者の総数を足して割った1人当たりの平均金額である。補足04:労働者(給与所得者)1人当りの所得税は、納税者1人当たりの平均支払額を所得税としている。住民税は均等割1人当たりの平均支払額と、所得割1人当たりの平均支払額を足した金額を1人当たりの住民税としている。補足05:労働者(給与所得者)1人当りの(折半分)自己負担 社会保険料(税)は、統計表「社会保険料(税)、健康保険料・年金保険料・介護保険料の支払い額の推移」内の全国健康保険協会(1世帯当り(年額:円))と厚生年金保険料(1世帯当り(年額:円))と介護保険料(1世帯当り(年額:円))を足した金額を用いている。単位A:労働者1人当りに出した給与の総額・平均給与・手取り給与の万円以下、千円単位については四捨五入して繰り上げてある。単位B:(折半分)会社負担 社会保険料(税)・(税金)所得税+住民税・(折半分)自己負担 社会保険料(税)の千円以下、百円単位については四捨五入して繰り上げてある。注意点:表示画面の制約上、当サイトでは雇用保険料の金額は掲載しておらず、手取り給与の金額を導きだす計算式に雇用保険料は含まれていない。 |
国民経済 (統計表)
◎ 社会保険料(税)、健康保険料・年金保険料・介護保険料の支払い額の推移 (年額) |
補足01:1997年・平成09年12月17日に介護保険法が成立、一部を除いて2000年・平成12年04月01日から施行された。介護保険料(1世帯当り(年額:円))は、介護保険(第2号被保険者)である満40歳~65歳未満の被保険者一人当たりの平均支払額である。単位A:全国健康保険協会・厚生年金保険料・国民健康保険料・国民年金保険料・介護保険料の千円以下、百円単位については四捨五入して繰り上げてある。注意点:表示外面の制約上、当サイトでは雇用保険料の金額は掲載していない。 |
国民経済 (統計表)
補足資料:医療費負担率・年金支給開始年齢・郵便貯金の金利・消費税率の変遷表 |
補足01:医療費負担率とは、医療機関から請求される医療費のうち被保険者個人が負担する割合の事である。1985年・昭和60年については確認が取れていないため不明としている。補足02:厚生年金と国民年金の支給開始年齢とは、年金受給資格のある加入者が年金の支給を受け始めることができる年齢の事である。1985年・昭和60年については確認が取れていないため不明としている。補足03:郵便貯金は、預入三年以上の定額貯金一年あたりの金利である。補足04:消費税は1988年・昭和63年12月に消費税法が成立、翌年1989年・平成元年04月に税率3%の消費税法が施行された。その後、消費税率は1997年・平成09年04月に5%に引き上げ、2014年・平成26年04月に8%に引き上げ、2019年・令和元年10月に10%に引き上げられた。 |